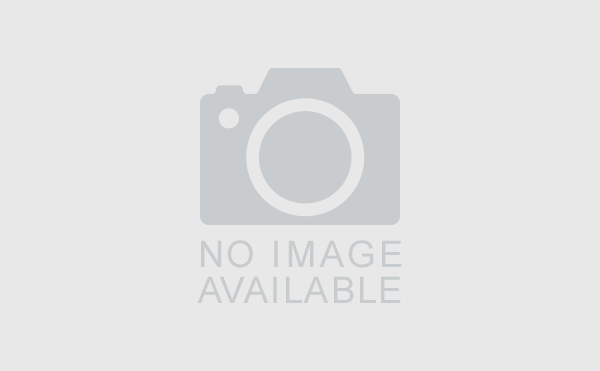ヨコハマタイワ36を開催しました。テーマは「無料とは何か?」
今日は連休明けのヨコハマタイワでした。(書いてから1週間後のアップになっちゃいました・・・)
8名募集で満席でしたが、2名欠席で6名。
個人的には6名が一番やりやすいと思っていて、4名から8名がいいかな、と思ってます。
4名だと僕が頑張ってしゃべらないといけなくて、8名だと僕が話すのは抑えないといけない、という感じがするんですよね。6名だと、僕が話したいときに自然体的に話に入れる感じ。あくまで僕の感覚ですが。
今回は、その場でテーマの候補を出してもらって、その中から決める流れ。
色々な候補の中から「無料とは何か?」に決まりました。また、採用されなかった候補の中に「ビル・ゲイツはなぜ全財産を寄付するのか?」というのもあって、そのあたりも絡めて話が進みました。
この「無料とは何か?」というテーマは、実は、何ヶ月か前の回で、このヨコハマタイワが無料なのはなぜ、という話があって、そこから続いていた話です。だから、僕もずっと気になっていたテーマで、必然的に僕が一参加者として語る機会が多くなりました。ここで話せて本当によかったし、6名という僕が話しやすい人数でちょうどよかったと感じました。
ということで、今回は、僕は進行役であるだけでなく、話の中身にも結構コミットしちゃったと思います。そういうのを避ける進行役も多いけど、まあ、それも「いちろう流」ということでご容赦ください。
話は、直接、「無料とは何か?」を考えるのではなく、「無料広告」や「寄付」のような無料な営みについて考えていく方向で進みました。そして、次第に、無料きもの着付け教室のような「無料広告」よりは、「寄付」や「ボランティア」のような善意の営みのほうに絞られていきました。
そのなかで、「寄付をする動機は『負債感』を精算するためなのではないか。」という話が出ました。「え、寄付なのに負債ってどういうこと?」と疑問が生じるだろう、なかなかのパワーワードなのですが、話を深めるにつれ、なるほど、と思える不思議な言葉でした。
ビル・ゲイツなら金稼ぎの能力、僕なら哲学カフェの進行役の能力。まあ、レベルは違えど、天賦の才を与えられた訳ですが、いわば「たまたま」偶然に与えられた訳です。だから、理由がないという意味で「不当」なもので、それは精算しなければならない。僕の言葉で表現するなら、世界から借りたものを返さなければならない。だから、ビル・ゲイツは金を寄付することで負債を解消し、僕ならば無料で哲学カフェを開催することで負債を解消する。
だから、この「負債感」は使命感とも言いかえることができて、これで「寄付」や「ボランティア」の動機の全てを説明はできないだろうけれど、なかなかいい線いっているような気がしました。
また、「してあげる」「させていただく」という言葉の不自然さの話にもなりました。「する」でいいのに、あえてこういう言い方が成立するってことは、そこに、何か動機があるのではないか。
これに対しては、能力の高低が関わっているのでは、という話になりました。能力が高い人から「してあげる」、能力が低い人は「させていただく」のように。
そこから、能力ではなく、その人の存在に着目すれば、そんな不自然な言い回しをする必要はなく、フラットになるのでは、という話にもなりました。
あと、前後関係は忘れたけど、このあたりの話と繋がる話として、ベトナムや中国やネパールでは、「ありがとう」という話は水臭いと受け取られがちという話も。伝聞の話なので真偽はわからないけれど、人とのつながりが強い社会では、そうなのかもな、と思いました。
「ありがとう」という言葉は、やってもらえたことを直ちに精算するということで、それは、お金を支払うことにも通じるものがあるような気がします。
一方で、アメリカ社会には、見返りなど気にせず、ただ寄付し、ボランティアをするような文化がある、という話にも。
そのあたりの話が結びつき、とりあえずの結論めいた話として、寄付やボランティアには、能力や資産の高低を慣らし、ひとりひとりの平等な存在に近づけていく働きがあるという方向の話になりました。また、家族や共同体内のメンバー間では、そもそも存在としての平等性があるから、お金のやりとり自体に無頓着になっていくという話もありましたね。
と、面白かったので、細かく書いてみました。
なお、あえて書くべきと思って書きますが、お一人、そもそも、こういうテーマに興味を持てないという参加者もいました。
その方は、採用されなかった「時間とは何か。」とか、前回やった「宇宙人はいるのか。」のようなテーマが好きで、今回のようなテーマ自体に興味を持てないという話でした。
これは、僕自身の問題意識としても、とてもよくわかるつもりです。
何度かどこかで書いているかもしれませんが、僕は、哲学カフェのテーマは、今回のような、人間・実生活に焦点を当てた倫理学的な話と、人間・実生活から離れた形而上学的な話があると考えています。
哲学カフェの参加者の多くは、倫理学的な話のほうが好きですが、一部、そうではない人もいます。実は僕もそっちのタイプで、まあ、どっちも面白いけれど、僕自身の本来の哲学的関心としては明らかに形而上学タイプです。まさに「時間とは何か。」みたいなことをずっと考えてます。
僕が哲学カフェを始めた動機のひとつは、僕が好きな話をしたい、というものがあったので、今後も、定期的に「時間とは何か。」、「宇宙人はいるのか。」のようなテーマを扱っていきたいと思います。
けど、やってみると、意外と人間・実生活密着型のテーマも面白いな、と思ってやってます。こっちのタイプのテーマのほうが、参加者の人生みたいなのが垣間見えて面白いんですよね。話も複雑化して、それを解きほぐそうと四苦八苦するのも面白いし。
ということで、皆さんお疲れ様でした。
あと、お菓子を持ってきてくれた方、ありがとうございます!