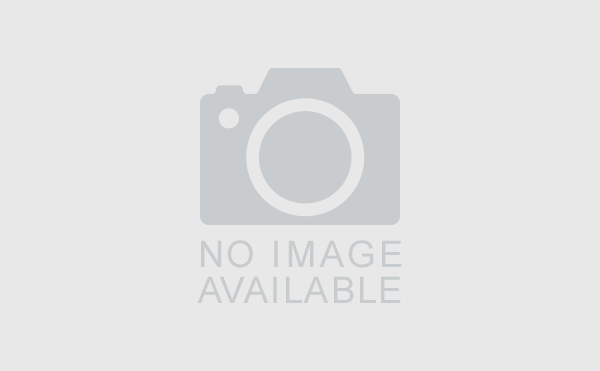今日は、ヨコハマタイワ38でした。
今日は、ヨコハマタイワ38でした。
今回は、長文でテーマ設定するという、ちょっと変化球な会だったのですが、始まる前に聞いてみたら、参加者9名中5名くらいが、哲学カフェ自体初参加ということで、ちょっと不安がありました。さらに、僕自身、飲み会やバーベキューが続いて、ちょっとお疲れ気味だったので。
けど、なんとか乗り切りました。始まればアドレナリンが出て?なんとかなるもんですね。偉いぞ俺。と言いつつ実は、参加者の皆さんに助けられたような気もします。初参加にもかかわらず、やってみたら、皆さん、ほんとに対話が上手なんですよね。若い方も年輩の方もいたけど、事前勉強したのかな、と思うくらいに素晴らしかったです。
ということで帰ったらゆっくり休もうと思ったけど、今日のことは記録に残さないと気持ち悪いし、選挙の期日前投票行かないといけないし(来週は旅行に行くので)、たまってる家事もしないといけないし……とパソコンに向かってます。
テーマは長文で、『親しい人が亡くなったとします。その人の記憶や考え方をそっくりそのままコピーしたAI対話ロボットがあったとしたら、亡くなった悲しみは軽くなるか?』というものでした。
これは、春くらいにSFっぽいテーマということで募集した際に応募があったテーマのひとつで、今日は、その提案者にもご参加いただきました。
僕は、事前にテーマを募集して、提案者に参加してもらうというやり方は、事前準備がめんどくさいこと以外は気に入ってます。当日、テーマ決めをすると、どうしてもテーマについて話す時間が短くなるし、かといって僕が適当に決めると、僕が進行役&提案者になってしまい、僕が主役になりすぎてしまう。提案者との調整が手間だけど、うまく、提案者にも主役になってもらえるところがいいな、と思ってます。
今回は、提案者が事前に資料を作成してくれて、コンパクトに自分の問題意識をまとめてきてくれました。この試みは、そういう問題意識の熱量があることが参加者に伝わるという意味で、とってもよかったと思います。
一方で、どこで資料を使うかという捌きがうまくできなかったのが僕の反省点でした。最初と、中盤の2回に分けて説明してもらったのですが、それよりも、最初から、すべて出し尽くしてもらったほうがよかった。なぜなら、対話において、議論をコントロールすることは不可能で、小出しにして議論をコントロールしようとするのは、小手先の対応すぎるから。
それよりは、多少、議論が不格好になってもすべて最初に出し切っちゃうほうがいい、と感じました。そのほうが、提案者の熱い思いが率直に表現され、それが他の参加者にも感染して、対話の場がいいものになるような気がします。
話の流れは、無機質なロボットで十分なのか、アンドロイドやクローンだったらどうなのか、という話と、そもそも、そういう置き換えが成功したとして、悲しみは軽くなるのか、という二つの話に分かれて進んでいったように思います。当然、二つに分かれておしまいではなく、「死の悲しみ」というところで二つの話は重なるのですが。
だから、今日の話の中心は「大事な人の死」とは何なのか、というあたりにあった気がします。そのうえで、クローンで「大事な人の死」がなかったことにできるなら、死を超えて維持されるのは何なのか、という話になっていきました。
維持されるのは、関係性である、魂である、空気である、「信じること」である、志である、といった様々な意見が出ました。どれなんでしょうね。僕はどれなのか答えを探すのも大事だけど、様々な意見が出ることを知るほうが大事なのかもしれない、とも思いました。人々が自分の頭できちんと考えていることを実感し、どこか頼もしさを感じました。
僕にとって大きな収穫は、ロボットで死の悲しみを軽くするためには、少なくとも、ロボットが、人間のようにともに生きて成長するのでなければならない、と気づけたことでした。確かに、仮に僕の子どもが死んで、その身代わりロボットができたとしても、それが単なる記憶再生装置では全然足りない。少なくとも、僕の子どもが生きていたとしたら、こんなふうに成長したかもしれない、と思えるくらいじゃないと全く満たされない。
そのためには、僕の子どもが、もし生きていたらそうしていたかもしれないほどには、他者と関わり、友情を育んだり、恋愛をしたりできるような外見をしていなければならない。そこまでできたなら、もしロボットと気づいていたとしても、そのロボットを新たな養子のように受け止め、少しは悲しみを軽くすることはできるかもしれない。
うちの近所に、同じ犬種の犬を何代も飼っている家があるのだけど、これと似たことを考えているのかもしれない。近所の人も、当然、同じ犬だとは思っていないだろうけれど、似た見た目であることで、悲しみが軽減されることもあるのかもしれない。
そんな話をしたところ、参加者から「生まれ変わりだと思っているのかも」という発言もありました。
ここからは、その場ではなく帰りながら考えたことなのだけど、きっと、悲しみを軽減するためには、そのような「物語」が必要なのではないだろうか。「生まれ変わり」や「天国」や「悲しみを軽減しようとしてロボットを作ってくれた制作者の愛情」とは、そういう「物語」装置のひとつなのかもしれない。
また、参加者が言っていたけれど、たしかに、悲しさとは複合的なものなのかもしれない。そしてその悲しみを構成するパーツのひとつくらいは、記憶の再生装置としてのコピーロボットという「物語」が、多少は緩和してくれるのかもしれない。けれど、一方で、そんな粗雑な「物語」で悲しみを緩和しようだなんて、僕の悲しみをなめるな、と怒りを招くかもしれない。
今回の長文テーマ設定については、参加者の何人かから、問題を絞りにくかった、という指摘がありました。たしかにそのとおりで、まあ、事前に予想していたとおりでした。この長文を、どう絞り込んでいくかがチャレンジングで、実際苦労しました。けれど、参加者のひとりひとりが、長文のテーマの中から自分だけの問題を見つけていく、というのも面白い試みだったと思います。別の長文だったらどうなるのか試したいので、近いうちにまた、長文テーマでやってみたいです。
最後に一言。お母さんと一緒に、小学生の子供がついてきてくれたけど、本人が退屈じゃなければ、こういうのもよかったと思います。正直、難しい言葉も多くて、わからないことばかりだったかもしれないけど、大人が真面目に変なことやっていると知ってもらえただけでもよかったかも、と思います。
僕としては、小学生であっても、最初から傍観者として排除しちゃうと、対話の場にそぐわないと感じたので、一応、参加者扱いとさせていただきました。そのうえで、対話にどこまで参加するかは、参加者としてのお子さん自身に決めてもらうべきだ、というのが厳しいかもしれないけれど、僕の考えです。
ということで、お子さんも含めて皆さんお疲れ様でした。これから掃除して選挙に行かないと!